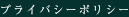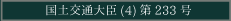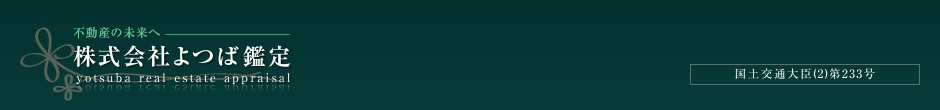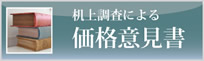セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、「第2の意見」のことであり、本人がより良い決断をするために、担当専門家以外の第三者専門家に意見を求めることを意味します。
セカンドオピニオンは医療現場において広く知れ渡っていますが、行うのは医師に限定されるものではありません。
たとえば、法律や税務などに関して、顧問弁護士や顧問税理士以外の専門家に意見を求めることなどが挙げられます。

セカンドオピニオンが存在するのは「世の中全てのことに唯一絶対はない」という真実があるからではないでしょうか。
ある一人の専門家の意見は、その人の意見にすぎないのであって、もしかしたら「その人以外の意見の方が自分にはしっくりくる」そんなこともあるかもしれません。
セカンドオピニオンは「自分でも納得できる」ためのひとつの方策なのです。
担当専門家に遠慮することなく、積極的に活用しましょう。
これからはセカンドオピニオンの時代です!
→費用
| ご注意 弊社サービスのセカンドオピニオンは、独自に評価額を出すものではありません。評価額を出すためには「鑑定評価」を行わないと分からないためです。 ですので、セカンドオピニオンは「この評価額より高い(低い)金額が適正と思われる」「この評価額は間違いで、いくらくらいが適正金額である」という内容のものではありません。 価額を求める場合は、「一般鑑定」などの鑑定評価となります。詳しくはこちらもご覧下さい→セカンドオピニオンが有効な場面 |
a.不動産鑑定評価とセカンドオピニオン
不動産鑑定評価におけるセカンドオピニオンとは、不動産鑑定評価書の内容に関して、評価担当不動産鑑定士以外の第三者である不動産鑑定士に意見を求めることをいいます。
自分で依頼・取得した不動産鑑定評価書に対する意見を求める場合もあれば、裁判などのように対立する相手から出された不動産鑑定評価書に対する意見を求める場合もあります。
なお、前者の場合であっても、担当した不動産鑑定士に遠慮する必要はありません。
大切なのは、「あなたが損失を被らないこと」なのです。
b.不動産鑑定評価の本質
不動産鑑定評価の本質は、「不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見である(不動産鑑定評価基準第1章第3節)」ということをご存じでしょうか?
これは、不動産鑑定評価は「査定」であって、「算定」ではないことを意味しています。
単なる計算をすることを算定といいます。それに対して、査定というのは判断を介在させることをいうのです。
したがって、担当不動産鑑定士の判断如何で結論は変わり得るものなのです。
「不動産鑑定士によって鑑定評価額が異なるのはおかしい」と思われる方がいるかもしれません。しかし、私たち不動産鑑定士は「10人の不動産鑑定士が同じ物件を鑑定評価して、価格が一致することはありえない」というのが本音ですし、現実に一致することはありません。それくらい不動産の鑑定評価というのは判断部分が多いといえます。
セカンドオピニオンとの関係で重要なのは、「個人の判断だからどのような内容でも問題はない」という認識は間違いであるということです。
c.不動産鑑定評価で重要なこと
不動産鑑定評価は、「合理性」をもってしかその評価結果の正しさを証明できません。
つまり、「不動産鑑定評価書の内容が合理的である以上、その結果である鑑定評価額は正しい」といえるのです。
これは、表現を変えるならば、「不動産鑑定評価書に不合理な点がある場合には、鑑定評価額の妥当性が認められにくくなる」ともいえます。
不動産鑑定評価書の不合理性には様々な観点があります。したがって、セカンドオピニオンによりこの多面的なチェックをしておくことが、安心・安全な不動産鑑定評価につながるのです。
このように、不動産鑑定評価書で一番大切なことは合理性の追求であり、不合理性の排除なのです。
d.不動産鑑定評価書の現実
あなたは、「高いお金を払って作ってもらった不動産鑑定評価書なのだから、間違いなんかあるわけがない」とお考えかもしれません。
残念ながら、これは間違った認識です。
どんなに大手の鑑定事務所が作成した不動産鑑定評価書であれ、所詮は人間の作成物にすぎません。間違いはあるものなのです。
もちろん、必ず間違いがあるとまではいいません。
しかし、「かなりの確率で不合理性がある不動産鑑定評価書が多い」という現実を知っていただいた方がいいでしょう。
弊社はこれまで多くの他社不動産鑑定評価書を見てきました。
その中で、「あまりにひどい」不動産鑑定評価書がたくさんあることに驚きました。
ときには「これで裁判を闘おうというのか?」と目を覆いたくなるものもありました。
不動産鑑定評価書をご利用になる方は、この不幸な現実を知るべきです。
セカンドオピニオンを行って、その結果、「不合理性が全く認められない」というのならば、それは喜ぶべきであり、安心してご活用頂ければいいのです。反対に、「多くの不合理性がある」というならば、裁判所に提出する前に、不動産鑑定評価書の妥当性を否定される前に、修正する必要があるのということなのです。
(1) 時代背景
不動産鑑定評価の歴史をひもとけば、価格が表示されただけのような書式という時代があったそうです。その後の手書きや和製タイプライターで不動産鑑定評価書を作成していた時代ならば、「それは不動産鑑定士の判断です」がまかり通りました。
しかし、パソコンが発達した頃には、不動産鑑定評価基準及び社会が熟成し、高度な分析と明快な根拠が求められるようになりました。
今は不動産鑑定士の判断に「根拠」と「合理性」が求められる時代です。
判断の背後にある合理性が認められない場合には、いとも簡単に「信頼できない」と否定されてしまうのです。
現代は「不動産鑑定士の判断」の一言で通る時代ではないのです。
(2) 専門的でわかりにくい
不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準というルールに則っています。
それゆえ、不動産鑑定評価書には難解な専門用語がたくさん出てくるのです。
専門用語を使わずに不動産鑑定評価書を作成するのは現実的には困難です。
そのため、一般の方が不動産鑑定評価書を読んでもわかりにくく、「間違いに気づかない」という現実があります。
また、不動産鑑定評価書の書式には規定がありません。どのような書式でもいいのです。必要記載事項という「最低限記載しなければいけない内容」があるのみなのです。
不動産鑑定評価書を見たことがある人であっても、書式が変わると内容を理解しにくくなります。私たち不動産鑑定士でさえも、他社の書式は手こずりますので、一般の方はなおさらだと思います。
わかりにくい不動産鑑定評価書をご自身でチェックするのはとても難しいことです。
セカンドオピニオンを有効活用して、不動産鑑定評価書の問題点は他の不動産鑑定士にチェックさせた方が無難ということなのです。
(3) 間違いが横行しているという現実
弊社ではこれまで「間違いだらけの不動産鑑定評価書」をたくさん見てきました。
本当に驚くほど間違いが横行しているのが現実です。
もちろん、作成者には間違っているという認識はないはずです。
みんな専門家としての誇りをもって不動産鑑定評価書を作成しているからです。
しかし、間違いは発生してしまう。
それはなぜかというと、不動産鑑定評価書は内容が複雑だからです。
それゆえ不動産鑑定評価書のボリュームが増せば増すほど間違いが生じやすくなるのです。
さらに、不動産鑑定評価書の間違いには様々なタイプがあることも間違いが横行する要因のひとつです。
誤字脱字といった形式的間違いのみならず、不動産鑑定評価書前半と後半での意見の矛盾や不動産調査ミスといった様々な内容に係わる間違いがあるのです。
不動産鑑定評価書は、人間の作成物にすぎません。
そして、それは大手の不動産鑑定事務所であっても、同じような間違いが発生する可能性を秘めていることを意味しています。
どこが発行したものであっても間違いがある可能性がある。
だからこそセカンドオピニオンが必要なのです。
(4) 「大手だから安心」とはいえない現状
平成24年9月7日付で、国土交通省土地・建設産業局企画課長から公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会長宛に「不動産鑑定評価等の適正な実施について」が発出されました(国土鑑第22号)。
これは、国土交通省が平成23年度において、鑑定評価モニタリングの一環として、REITなどに提出している鑑定評価を行った不動産鑑定業者に対する立入検査を行った結果、改善を要する内容が見られたことから、業界団体である連合会に協会会員である不動産鑑定業者への周知を指示したものです。
つまり、証券化対象不動産に係る不動産鑑定評価書において、問題点が続々出てきたという事実があるのです。
言うまでもなく、現在証券化対象不動産評価を行っているのは、大手又は準大手の鑑定業者です。
しかし、現状は国土交通省から「適正な実施」を指示されてしまうほど問題点が出てきてしまうのです。
「大手だから間違いはないだろう」というのは依頼者側の期待に過ぎないというのが現状なのです。
(5) 公開(提出)する前ならば訂正が可能
不動産鑑定評価書は、見せる(提出する)相手方がいることが一般的です。
しかし、いったん相手方に見せてしまえば、引っ込めることはできません。
「あれは間違いでした」ではすまないのです。
みなさんは、上記で「間違いだらけの不動産鑑定評価書の現実」を知りました。
では、どうすべきでしょうか?
「間違いないようにお願いしますね」と一言付言した上で依頼すれば大丈夫でしょうか?
答えがNoであることは明らかです。

誰も自分の提出した不動産鑑定評価書に間違いがあるなんて想定していません。
それでも間違いがあるのが現実です。
だったら、セカンドオピニオンを活用して、公開する前に間違いを第三者にチェックしてもらうのはどうでしょうか?
公開前ならば、いくらでも訂正は可能です。
間違えたものを公開してあとで対応に追われる(又は不利な状況になる)よりも、多少のコストをかけてでも事前に間違いをつぶしておいた方が結局は得をするということもあると思います。
(A) 民間における活用事例
(1) 裁判や調停における自分方の不動産鑑定評価書のチェック
(2) 裁判や調停における相手方の不動産鑑定評価書のチェック
(3) 裁判や調停における鑑定人の不動産鑑定評価書のチェック
(4) リートに提出された不動産鑑定評価書のチェック
(5) 相続税の時価申告など、税務署に提出予定で準備された不動産鑑定評価書のチェック
(6) 固定資産税の時価申告など、都税事務所(市役所税務課)等に提出予定で準備された不動産鑑定評価書のチェック
(7) その他、疑問を感じる場合に
(B) 公共における活用事例
(1) 裁判所に提出された不動産鑑定評価書のチェック
(2) 税務署に提出された不動産鑑定評価書のチェック
(3) 市役所税務課等に提出された不動産鑑定評価書のチェック
(4) その他、疑問を感じる場合に
弊社では、これまでに訴訟鑑定研究会として裁判等で培ったセカンドオピニオンに係るノウハウがあります。
下記独自基準に基づき、丁寧なチェックに裏付けされたセカンドオピニオン意見書を発行いたします。
その技術の高さにきっと驚かれることでしょう。
※セカンドオピニオン意見書サービスは訴訟鑑定研究会とは異なります。
(1) 鑑定法適合チェック
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「鑑定法」)、同施行規則に反している不動産鑑定評価書は論外です。
しかし、資格試験合格後は勉強を怠る資格者は意外に多いものです。
鑑定法の改正があったことすら知らない不動産鑑定士の存在をみなさんは知る必要があるでしょう。
(2) 鑑定評価基準適合チェック
不動産鑑定評価基準(以下「基準」)は、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たって準拠すべき拠り所です。しかし、基準違反の不動産鑑定評価書が横行しているのも悲しき事実です。
不動産鑑定評価基準は法律ではないため、基準に準拠していないからといって、法律違反となるわけではありませんが、有利に働くことは一切ありません。
(3) 表示ミスチェック
誤字脱字といった表示ミスは、見る人の心証を悪くします。
表示ミスがたくさんあるような不動産鑑定評価書を「信頼性に足る」と判断する人は少ないでしょう。
(4) 分析の妥当性チェック
価格形成要因の分析は、第一義的には担当不動産鑑定士の判断によるところが大きいものです。しかし、たとえば最寄り駅の判定で、合理的理由がなく距離が最も近い駅を採用していない場合もあるなど、不合理な分析をしている不動産鑑定評価書を過去に見てきました。
不動産鑑定評価書の合理性の検討に際しては、この分析の妥当性チェックは欠かせないものとなっています。
(5) 査定の妥当性チェック
価格の査定部分は、最も担当不動産鑑定士の判断によるところが大きいところです。
しかし、この内容こそが最終的な鑑定評価額の大小に直接的に影響していることから、この部分の検討なしでは効果が半減してしまいます。
たとえば、原価法の適用における「採用現価率は妥当性の範囲か否か」。これは不動産鑑定士だからこそわかり得る内容です。
不動産鑑定士だからこそ不動産鑑定士の考えていることが手に取るようにわかるのです。
(6) 調査ミスチェック
調査ミスは、評価担当鑑定士と同様に、実際に現地又は役所へ出向いて確認しないと判明しません。
しかし、出張調査はコストアップにつながります。それゆえ、現地又は役所へ行って確認する当サービスはオプションとして用意しています。
なお、調査ミスは「作業者」の単純ミスであるため、どんなに大手の不動産鑑定事務所であったとしても、完全に防ぐことはできません。過去には、最大手の不動産鑑定業者が裁判所に提出した不動産鑑定評価書において、裁判官に容積率の調査ミスを指摘され、「合理性に欠ける」と否定された事例があるくらいです。
調査ミスは不合理さの決定打となり得るだけに、必要に応じてオプション付加をご検討ください。
(7) 鑑定評価額の妥当性判定
鑑定評価額の妥当性は、上記を総合的に勘案してはじめて説得力のある結論を出すことが可能となります。
鑑定評価額の妥当性は、その過程の妥当性をもってしか証明できません。
合理性がない不動産鑑定評価書に鑑定評価額の妥当性を認めることはできないのです。
※セカンドオピニオンは鑑定評価ではないため、独自に評価額を出すものではありません。
(8) 再評価チェック
同じ物件を後日再度鑑定評価することを再評価といいます。
この再評価を行う際には、「再評価ならでは」の要注意ポイントがあることをご存じでしょうか?
実は、再評価というのは、当初評価よりも慎重に評価しなければいけないのです。
なぜなら、評価の整合性が特に重要となり、問題点が浮き彫りになってしまうからです。
弊社のセカンドオピニオンでは、再評価物件に係るセカンドオピニオン専用のチェック項目を用意してありますので、どうぞご安心ください。
セカンドオピニオン意見書費用(弊社報酬)は、評価類型に応じて異なります。
これは、基本的には作業量と複雑さの違いによるものです。
評価類型は、不動産鑑定評価書内に記載されている「不動産の種別・類型」欄をご確認ください。
また、高コストにつながる現場調査につきましては、オプションとさせていただきました。鑑定評価書の書面のみならず、現場確認事項までもチェックして欲しいというニーズにも対応いたします。(基本料金・オプション料金については、対象の評価書のボリュームによって変わります。)
| 区分 | A | B | C | D | |
| 評価の類型 | 更地・建付地・建物自体・農地・林地・宅地見込地 | 借地権・底地・区分地上権・新規地代 | 新規家賃・自用の建物及びその敷地・貸家及びその敷地 | 継続家賃・継続地代・区分所有建物及びその敷地・自用の建物及びその敷地(含借地権)・貸家及びその敷地(含借地権) | |
| 基本料金(税込) | 110,000円~ | 121,000円~ | 132,000円~ | 143,000円~ | |
| オプション料金(税込)(※1)(※2) | |||||
| 現地調査 | 11,000円~ | ||||
| 事例調査 | 22,000円~(※3) | ||||
| 役所調査 | 11,000円~ | ||||
※1:オプションのみでの依頼は受けかねます。
※2:一都三県以外は別途交通費を申し受けます。
※3:取引事例の地番が特定されていない場合は、取引事例が確認できない場合があります。
(1) お問合せ
まずは物件の概要についてお知らせください。
お問合せフォームから、もしくは直接お電話ください。
(2) お見積もり
誤解のないよう、事前に報酬見積もりをご確認ください。
(3) 正式なご依頼
正式なご依頼があるまでは、一切料金は発生しません。
(4) 書類送付
お手持ちの不動産鑑定評価書をご郵送又はメール送付してください。
お送りいただくのは、不動産鑑定評価書原本でなくても結構です。その際は、表紙を含め全ページのコピーをお送りください。
(5) 作業
書類到着後7~10日程度お時間をいただきますが、状況に応じて早期対応も可能です。
(6) 納品
報告書をご覧いただきながら、分析結果についてご説明いたします。
遠方の場合は、メールや電話等でも対応させていただきます。
(7) アフターフォロー
納品後でもいつでもご連絡ください。
※書面作成、出張等については別途有料にて承ります。